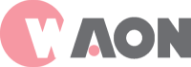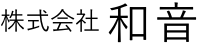「AIがケアプランを作る」―そんな話を聞いて、皆さんはどう感じるでしょうか。
「人の気持ちをAIが分かるわけない」 「現場でそんなの通用するの?」 そう思う方も多いかもしれません。でも、実はもう始まっています。
厚労省が令和6年度に実施した実証事業では、AIがアセスメント情報を整理し、過去の類似事例と照らし合わせてケアプラン案を提示する支援ツールが検証されました。 現在は自治体や事業所への情報提供が始まり、“現場での試用・フィードバック段階”です。
先日、AIに「このアセスメントで抜けている視点は?」と聞いてみたんです。 すると、厚労省の「適ケア」マニュアルをもとに、的確なアドバイスが返ってきました。正直、衝撃でした。 「え、これ…誰でもできるやん」と思ったくらいです。
これまで、アセスメントの抜け漏れに気づくのは、経験や直感に頼る部分が大きかったですよね。 でも今は、AIが厚労省のマニュアルを読み込んで、冷静に指摘してくれる。 「時代が変わったのです。
では、そんな時代に、ケアマネに求められる力とは?なんなんでしょうか。気になります。
AIが制度を読み込み、利用者情報を整理する時代だからこそ、 ケアマネには「利用者の本心を引き出し、問題の本質を見抜き、それを言語化する力」が求められると思います。
- 本人が言葉にできない思いを、対話の中で引き出す力
- 表面的な課題の奥にある背景や構造を見抜く力
- それらを根拠として、ケアプランに落とし込む力
この3つの力は、いまのところ、AIでは代替できません。AIが“平均”を示すからこそ、 ケアマネは、目の前の“その人”をしっかり見つめ、 その人らしさに寄り添う支援を考える存在であり続けます。AIは脅威ではなく、“使いこなす道具”です。 ケアマネの本質は、「人の言葉にならない思いを読み取る力」。 急速に進むAI時代の中でも、 “人”を支える仕事は、これからもケアマネの手の中にあります。